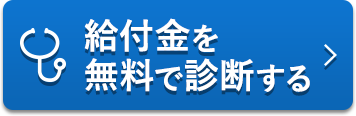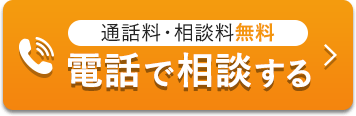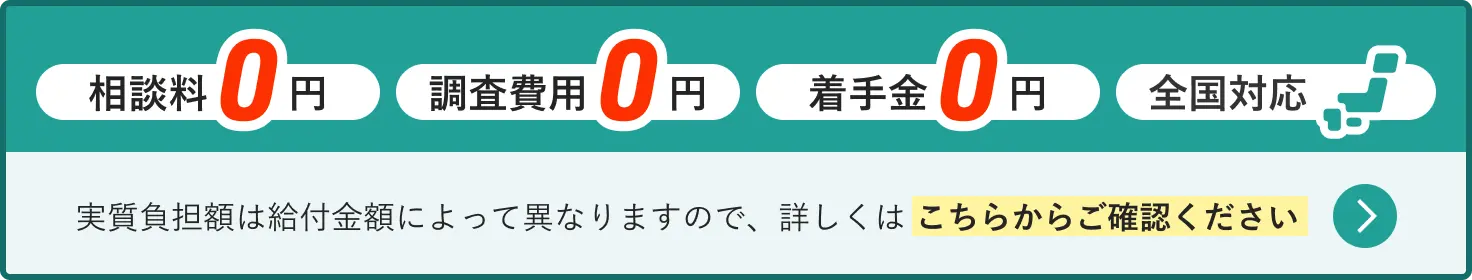B型肝炎の給付金・訴訟の弁護士相談はベリーベスト法律事務所におまかせください。
- B型肝炎 給付金請求訴訟
- 弁護士コラム これでわかった!B型肝炎訴訟
- B型肝炎訴訟の除斥期間|20年で給付金・支払負担額は大きく変わる
弁護士コラム これでわかった!B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟の除斥期間|20年で給付金・支払負担額は大きく変わる
- 給付金請求
- B型肝炎訴訟
- 除斥期間

除斥期間(じょせききかん)とは、民法で定められた、一定の期間を過ぎると権利そのものが消滅してしまう期間のことです。
B型肝炎訴訟においては、「発症から20年が経過すると給付金が大きく減額される」としてこの除斥期間(現在は「時効期間」)が問題になるケースがあります。また、除斥期間の経過前と経過後では、受給できるB型肝炎給付金の金額が大きく異なる点にも注意が必要です。
この記事では、除斥期間が設けられている理由や、除斥期間前後の給付金の金額などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、B型肝炎訴訟における給付金の除斥期間とは?
そもそもB型肝炎給付金の「除斥期間」とは何なのか、どのくらいの期間なのか、なぜ設けられているのかなど、除斥期間についての基本的な事項を押さえておきましょう。
-
(1)20年が経過すると給付金の金額が大きく減る
B型肝炎給付金は、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」といいます。)という法律に基づいて支給されます。
この特措法には給付金額の定めがありますが、20年が未経過の給付対象者と、20年が経過した給付対象者を比較すると、20年が経過した給付対象者に対するB型肝炎給付金が大きく減額されるというルールがあります。
この20年の期間のことを、民法の考え方を基に「除斥期間(じょせききかん)」と呼んでいます。 -
(2)なぜ除斥期間が設けられているのか
B型肝炎給付金において、20年という期間が基準とされているのは、もともとB型肝炎給付金が「不法行為に基づく損害賠償」としての性質を持っていることに由来しています。
その根拠となっていたのは、以下の改正前民法第724条です。【改正前民法】
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
上記のように、民法においては、「不法行為の時から二十年を経過」したか否かを基準に、大きく扱いが変わる定めになっています。そのため、特措法においても20年という期間を基準に定めているのです。
-
(3)除斥期間と時効期間
上記のように、以前は「不法行為の時から20年」が「除斥期間」とされていました。
しかし2020年4月1日の改正後は、下記のように「時効期間」に統一されました。【改正民法】
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
除斥期間と時効期間の違いは、簡単に説明すると次のようになります。
除斥期間と時効期間の違い 除斥期間 時効期間 原則として時間の経過により当然に権利が消滅する。 「完成猶予」や「更新」の手段により時効期間が延長されることがある。
さらに、時効が成立していても、事情によっては、その時効が信義則違反あるいは権利濫用であるとして制限される可能性もある。この改正によって、より被害者が救済されやすくなることが期待されています。
-
(4)B型肝炎訴訟における除斥期間
上記のように、B型肝炎給付金が不法行為に基づく損害賠償としての性質を持つことから、本来は不法行為当時の改正前民法の規定に従い、不法行為の時から20年を経過すると請求できなくなるのが原則です。
ただし、実際には20年の経過後にB型肝炎給付金を請求する被害者も多かったことも事実です。
こうした被害者を一切救済しないということは、国が引き起こした事態・被害の深刻さから考えて無責任ではないかという議論がありました。
そのため、20年が経過した後であっても、金額自体は大きく減額されるものの、特例的に国から被害者に対する一定の給付を行う内容の合意がなされました。
このように、B型肝炎訴訟においては、民法における時効期間・除斥期間と全く同じものではなく、その考え方を基にした独自の規定であるともいえます。
2、除斥期間の20年の経過前後でB型肝炎給付金の金額はどのくらい変わる?
それでは、20年の経過前後で、実際に受け取ることのできるB型肝炎給付金の金額がどのくらい変わるのかについて見ていきましょう。
-
(1)死亡・肝がん・肝硬変(重度)の場合
給付対象者の中でもっともB型肝炎給付金の金額が高い「死亡・肝がん・肝硬変(重度)」のケースでは、20年の経過前であれば3,600万円の給付金を受け取ることができます。
一方、20年経過後の場合には、B型肝炎給付金の金額は900万円にまで減額されます。 -
(2)肝硬変(軽度)の場合
「肝硬変(軽度)」のケースでは、20年の経過前であれば2,500万円の給付金を受け取ることができます。
一方、20年経過後の場合、「現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの」に該当する場合には600万円、そうでない場合には300万円の給付金を受け取ることができます。
「現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの」とは、現状は治療はしてないが、B型肝炎に関してのインターフェロン治療、核酸アナログ製剤、ステロイドリバウンド療法またはプロパゲルマニウムのいずれかの治療歴が医療記録等から認められる方をいいます。 -
(3)慢性肝炎の場合
肝硬変には至らないものの、「慢性肝炎」を抱えているケースでは、20年の経過前であれば1,250万円の給付金を受け取ることができます。
一方、20年経過後の場合は、「現に当該B型肝炎にり患しているもの又は現に当該慢性B型肝炎にり患していないが、当該慢性B型肝炎の治療を受けたことがあるもの」に該当するかどうかでB型肝炎給付金の金額が異なり、該当する場合には300万円、そうでない場合には150万円の給付金を受け取ることができます。 -
(4)無症候性キャリアの場合
具体的な症状は出ていないものの、B型肝炎ウイルスに持続感染している「無症候性キャリア」のケースでは、20年の経過前であれば600万円の給付金を受け取ることができます。
一方、20年経過後の場合、無症候性キャリアの方が受け取ることができるB型肝炎給付金は50万円に過ぎません。
ただし、20年経過後の無症候性キャリアの方は、定期検査費用などについて、国から一定の助成を受けることができます。
3、B型肝炎訴訟の給付金除斥期間になる20年のカウント起算点はどこから?
これまで説明したように、B型肝炎給付金においては20年を経過しているか否かによって大きく金額が変わります。そのため、この20年の期間をいつからカウントするか(起算点)は非常に重要です。
-
(1)「不法行為の時」が起算点
B型肝炎給付金において請求額の減額の基準となる20年の期間は、民法における不法行為の時効期間(改正前においては除斥期間。)に合わせて、「不法行為の時」から起算するものとされています。
普通に考えれば、「不法行為の時」とは「感染した時」、つまり一次感染者の場合は集団予防接種を受けた時、母子感染者(二次感染者)の場合には出生時となりそうです。
しかし、B型肝炎の実態として、感染から相当な時間が経過してから具体的な症状が現れるというケースも多数見られます。
このような実態を踏まえると、感染時を不法行為の時として機械的に20年の期間経過により救済を制限してしまうのは、あまりにも被害者保護に欠けるといわざるを得ません。
そこで、患者の病状に応じて、一定の場合には20年の期間の起算点を後ろにずらす解釈が取られています。 -
(2)【ケース別】20年の期間の起算点
被害者の症状に応じた20年の期間の起算点を具体的に見ていきましょう。
【ケース1】無症候性キャリアの場合 無症候性キャリアの場合は、20年の期間の起算点は原則どおり「感染時」、つまり一次感染者の場合は集団予防接種を受けた時、母子感染者(二次感染者)の場合には出生時となります 【ケース2】慢性肝炎などを発症した場合 慢性肝炎などを発症した方については、その症状が発生した日が20年の期間の起算点となります 【ケース3】亡くなった場合 B型肝炎ウイルスへの感染が原因で亡くなった方については、死亡日が20年の期間の起算点となります
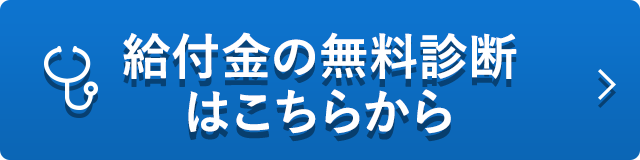
4、慢性肝炎などを再発した場合、20年の期間はいつから起算される?
B型肝炎ウイルスへの感染が原因で慢性肝炎などを発症した方が、一度治癒した後に再発を引き起こした場合、20年の期間の起算点は1度目の発症と2度目の発症のどちらになるのでしょうか。
-
(1)原則として最初の発症時から20年の期間が進行する
再発の場合に20年の期間をいつから起算するかについては、以下の裁判例が示されています。
最初に世間を沸かせたのが、福岡地裁平成29年12月1日判決です。
この裁判では、まさに1度目の発症時と2度目の発症時のどちらが20年の起算点となるかについて争われ、判決は、再発時を起算点として原告側が勝訴し、話題を呼びました。
しかしながら、同判決の控訴審である福岡高裁平成31年4月15日判決では、原審の判決を覆し、1度目の発症時が起算点であるとの判断で、原告側の逆転敗訴となりました。それ以降は原告の敗訴例が続いているようです。
福岡地裁令和2年6月23日判決でも、慢性肝炎の再発や長期継続は、病状の進行・拡大として当初の感染時に予見可能であることなどを理由として、20年の期間の起算点は1度目の発症時であると結論づけました。
今後上級審で異なる判断が示される可能性は残りますが、現時点での解釈としては、再発時の20年の期間の起算点は、原則として当初の発症時と考えるのが妥当でしょう。 -
(2)最初の発症とは質的に異なる再発の場合には再発時から起算
ただし同判決では、「再発時に質的に異なる損害が生じたとはいえないこと」についても、20年の期間の起算点を当初の発症時とする理由として挙げています。
このことを反対解釈すると、再発時の症状が当初発症時の症状と質的に異なるものである場合には、20年の期間の起算点は再発時になると考えられます。
たとえば、再発時の症状が当初発症時に比べて極端に重い場合など、当初発症した症状の延長線上にあるものとは考えられないケースでは、20年の期間の起算点を再発時としてB型肝炎給付金を請求できる可能性があるかもしれません。
5、除斥期間20年の期間とは別に、特措法上の請求期限がある
B型肝炎給付金を請求するにあたっては、20年の期間は給付金の金額を左右する非常に大事なポイントです。
一方で、20年の期間以外にも、B型肝炎給付金を請求するうえで注意しなければならないのが、特措法上の請求期限です。
-
(1)2027年3月31日までの訴訟提起等が必要
B型肝炎給付金に関する特措法第5条第1号では、2027年3月31日までに訴訟を提起して給付金の請求を行わなければならないと定めています。
B型肝炎給付金制度における「請求」は、以下のような手続きの流れで進みます。
訴訟提起→国の責任認定→和解成立→給付金支給
なお、2027年3月31日より前に訴訟を起こしても、発症から20年以上経っている場合は「時効期間」となり、減額対象となる可能性があります。
したがって、「時効期間」「請求期限」どちらの期限にも注意が必要です。給付金を最大限に受け取りたいのであれば、弁護士に相談し「できるだけ早く訴訟を提起すること」が重要となります。 -
(2)請求期限は延長される可能性がある
実は、特措法の請求期限については、もともとは「2022年1月12日まで」とされていたものが延長され「2027年3月31日まで」となっています。
推定されるB型肝炎感染被害者の数に比べて、実際に給付金を受け取った被害者の数があまりにも少なかったということが、当時期限が延長されたことの背景にあります。
B型肝炎給付金を受け取った被害者の数は依然として十分とはいえないため、再び請求期限が延長される可能性はあるでしょう。しかし、延長するかどうかはあくまでも立法府の判断により決定されるため、確実なことはいえません。
そのため、現行法で定められている期限までにB型肝炎訴訟を提起しておくことをおすすめします。
6、B型肝炎訴訟はベリーベスト法律事務所に相談を
B型肝炎訴訟については、ご自身で訴訟を提起するのは大変な労力を要しますので、弁護士に依頼をして準備を進めることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟を請け負った経験を豊富に有しており、訴訟提起の準備から給付金の受給まで、依頼者の方をさまざまな面からサポートいたします。
弁護士費用についても、B型肝炎訴訟については完全成功報酬制を採用しており、着手金や相談料等はいただきません。
B型肝炎ウイルスへの感染でお悩みの方は、時効期間や特措法上の請求期限との関係もありますので、できる限りお早めにベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。